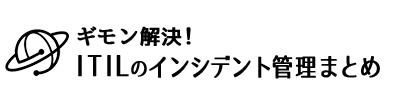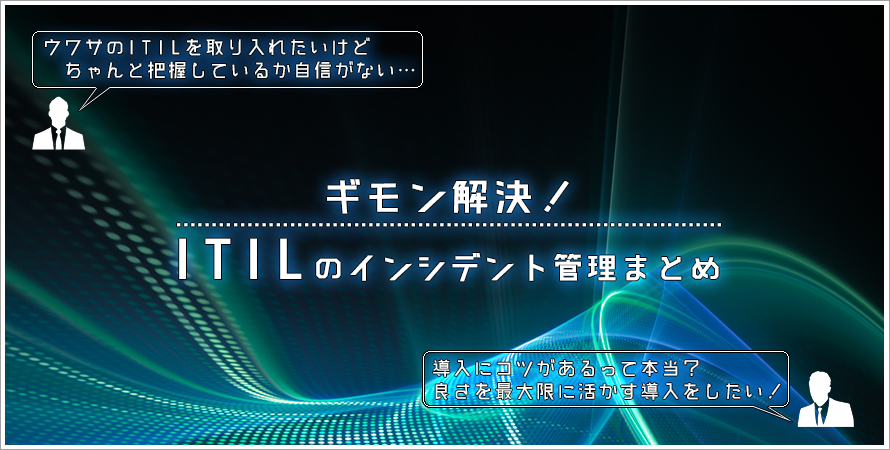
ギモン解決!ITILのインシデント管理まとめ
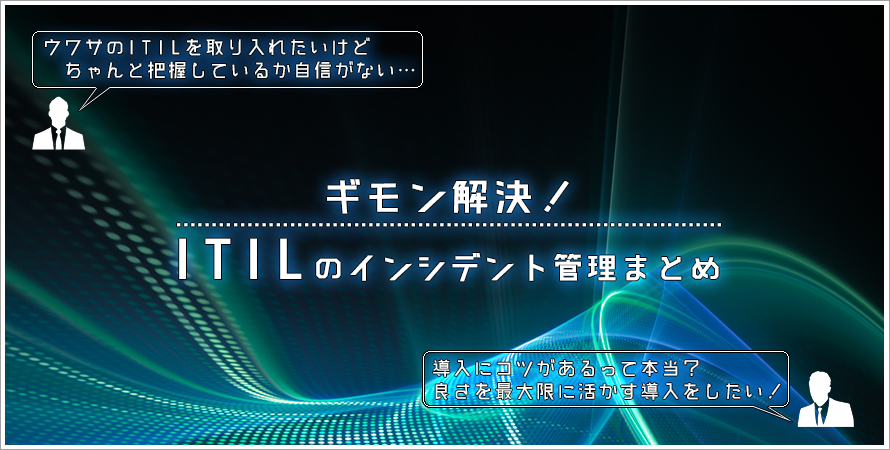
TOP > ITILのインシデント管理について > ITILインシデント管理をわかりやすく説明
ITILインシデント管理をわかりやすく説明
企業でのIT運用の方法論である「ITIL」ですが、そもそもITIL自体がよく分からないという人も多いでしょう。
理解するためにはまず、企業のIT運用で起こっている問題に注目する必要があります。
現在多くの企業で問題になっているのが、IT運用のコストです。
特に曖昧に運用されていると経理財務から目の敵にされがちで、無駄金を使っていると削減要求されてしまうこともしばしば。
サーバーやネットワークを構成したのは良いけれど、情報が共有されていないために有効活用できていない例。
トラブル時に特定の人間にしか対処出来ないばかりに、解決するまでに非常に長い期間がかかってしまったりする例。
こうした事例が原因で、やり玉に上がりやすいのがIT運用部門です。
突発的なトラブルは避けられませんが、優先度が現場に伝わらず業務がおろそかになったりすると、ユーザー満足度が低下する危険もあります。
それでもほとんどの企業でIT業務を独立部門や子会社が担当しているため、明確な業務目標も設定されないまま「言われ仕事」になっています。
長引く不況で組織からのコスト削減圧力が高まり、追い詰められているIT部門や子会社は数知れません。
この状況を正しく修正するために、運用業務をシステム化し、効率化するための指針がITILです。
ITILは「IT Infrastructure Library」の略ですが、元々はイギリスで始まった、投資に見合うITサービスのガイドラインです。
現在も英国商務省が管理しているものですが、英国出版局から書籍が発行され、世界各国で啓蒙活動が行われ来ました。
注目されているテーマはサービスサポートとサービスデリバリで、サービスサポートの中で「インシデント管理」が謳われています。
肝心なのは、ITILは「ITの企業内サービス」だという観点からIT管理業務を捉えているという点。
ITILは規格ではなく、より良いサービスを行うためのノウハウ本といった存在と考えれば良いでしょう。
インシデント管理の「インシデント」とは、顧客からのサービスリクエストのことです。
IT運用の中では、日々あらゆる要求や問い合わせが来たり、障害の報告があったりしますよね。
インシデント管理では、何があってもITサービスの停止を最小限に抑え、まず真っ先にサービスを優先させて回復することを重視します。
つまり、いきなり深いところにハマるのではなく、例え原因が解明されなくともサービスは何とか使える状態にするのを優先するということ。
また、将来起こるかもしれないインシデントを先んじて調査し、インシデントが発生しないよ減少させることも重要としています。
必要であればシステム変更管理のプロセスにも手を付けること。
実際に変更する際には設計から構築、検証までリリース管理を徹底することも必要です。
構成管理は変更管理と連携しながら、あらゆるハードウェアやソフトウェア構成などを格納する管理データベースを保障することです。
こうした一連の作業がサービスサポートであり、実際にはどんなサービスにとっても当たり前の考え方と言えるでしょう。