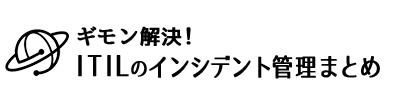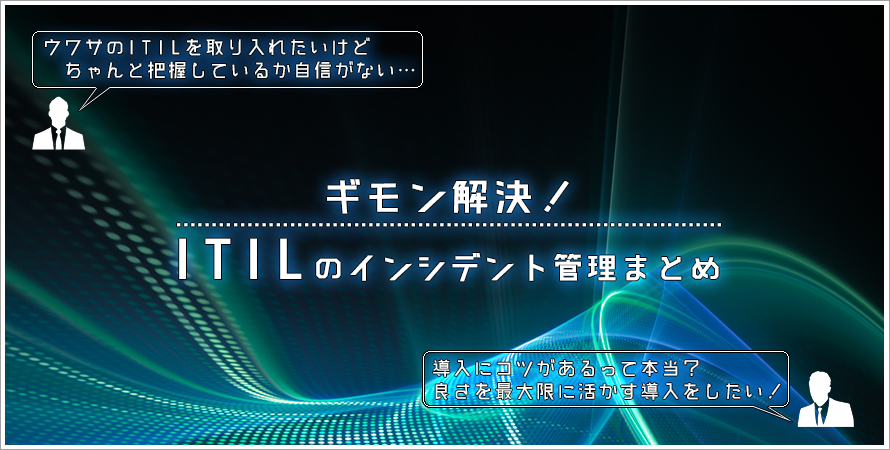
ギモン解決!ITILのインシデント管理まとめ
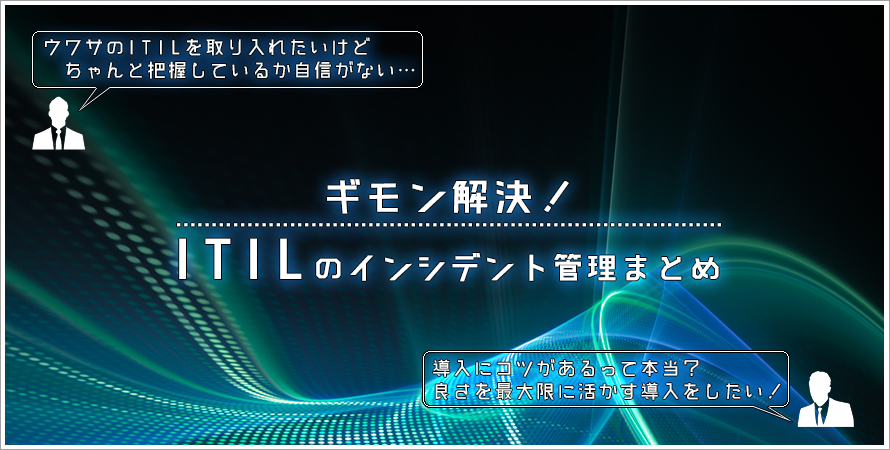
TOP > ITILのインシデント管理について > ITILのインシデント管理について
ITILのインシデント管理について
インシデント管理に問題のある現場では、往々にして情報の一元化がなされていません。
例えばユーザーからサービスリクエストを受けた場合、受付はそこでメモを取り、関係者へ電話やメールなどで連絡をします。
受け取った開発や運用担当部署では、それぞれ独自の方法で情報を管理し、最終的には別のフォームで報告書を作成。
管理責任箇所へは報告書での事後報告となります。
一つの案件に対し複数の部署で複数の情報管理がなされ、それぞれバラバラに更新されていますね。
しかも管理責任者がその内容を知るのは、ずっと後になってからです。
これでは情報が分散し、その都度サービス品質にバラつきが出ますし、開発部署はユーザーの存在を無視して障害対応が優先になります。
当然連絡は遅れますし、報告も遅れや漏れが出るでしょう。
これが個別対応による、旧来のサービスサポートの問題点です。
真っ先に優先すべき障害管理を効率化するためには、何をすべきでしょうか。
まず、関係各部署に共通の管理基盤を設け、連絡方法やルールを策定します。
報告書という定型フォームに整えることに負担を掛けず、情報の伝達を最優先することが重要。
管理責任者がリアルタイムに全体の状況を把握し、的確な指示と判断が出来る状況にする必要があります。
こうした一連の連携も含めて行われるのが、ITILのプロセスの中の一部分であるインシデント管理です。
インシデント管理は1プロセスであり、それ単体で企業に導入されるべきものではありません。
ITサービス品質向上と捉える節がありますが、組織として安定したサービスサポートを行うためには単体では意味がありません。
インシデントに基く問題管理の他、変更管理、リリース管理、構成管理などを含めて、トータルで組織的に活動出来て初めてITILです。
目先にばかり目を取られると、枝葉を見て幹を見ずということになります。
何事も運用ルールは必要ですが、がんじがらめにするとまず浸透しません。
また、情報共有で最初に直面する課題が各担当の文章力であるというケースは少なくありません。
第3者が読んでも理解出来ない文章や、専門部署にしか分からない内容は、せっかくシステムがあっても情報の共有化にはつながりません。
結局、最終的には運用する「人」の努力がなければシステムは活かされないのです。
文章は常に人間がモニタリングし、管理者がその都度担当者へ指導していくしか方法はありません。
特にインシデント管理はインシデントをすべて記録し、障害をなるべく早く解決し、するためのプロセスです。
また、そもそもの発生件数を減らすのが問題管理です。
いずれにしても、何が起こっていて、どうすれば解決出来るのか、同じ問題が懸念されるのはどの部分かといった分析情報の共有は必須。
読んでも理解出来ない内容では、すべてが水の泡になってしまいますね。